病理診断科
診療内容・特色
病気の適切な治療のためには、病気の正確な診断が不可欠です。病気を持つ患者さんの体から採取された臓器(例えば胃癌患者さんの胃など)や組織・細胞を、肉眼あるいは顕微鏡で観察し、この病気が何であるか、どのくらい進行しているかなどの判定を下すことを病理診断といいます。
病理診断は、患者さんの治療方針を決める重要な行為であることから、医師が行う「医行為」であることが明確に定義されており、医師でなければ行うことはできません。病理診断を専門とする医師(病理医)は、患者さんに直接お会いすることはありませんが、患者さんの病変(病気の起こっている場所)から採取された組織や細胞から作製した顕微鏡標本(プレパラート)を観察し、その細胞の配列や形態をもとに病理診断を行います。主治医は、病理医によって報告される病理診断結果を受け取って初めて適切な治療を開始できるのです。
当院においては2012年12月より病理診断科を標榜し、診療科の一つとして病理診断業務を行うことで日常診療に貢献しています。
おもな診療内容
病理診断科では、年間約21,000件の病理診断業務(組織診断約9,000件、細胞診断約12,000件)を行うとともに、カンファレンス(症例検討会)等を通じて院内の各診療グループとも密接な連携を取り、医療チームの一員として患者さん一人ひとりの治療方針の決定に寄与する情報を提供しています。
各病理医はそれぞれ専門領域を持ち、最新の知見を加味した正確な診断を行うとともに、必要に応じて外部コンサルテーションシステム(日本病理学会、国立がん研究センターなどで組織される、難解症例のためのセカンドオピニオンシステム)を利用しながら、診断レベルの向上を目指しています。
診断業務を通じて得られた新たな病理学的知見は、関連学会や専門誌に発表することで広く院外にも発信し、医療の進歩に貢献し続けています。
スタッフ

- 科長
教授 - 笹島 ゆう子
人体病理全般
婦人科・乳腺・皮膚の病理
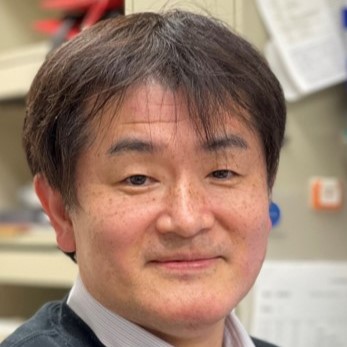
- 病院教授
- 斉藤 光次
人体病理全般
肝・胆・膵の病理
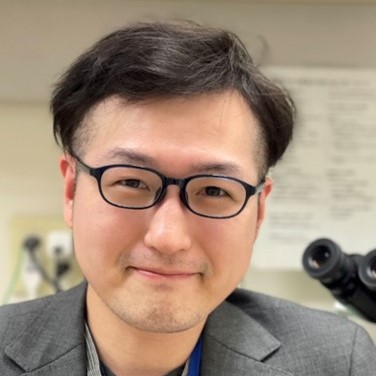
- 助教
- 石田 毅
人体病理全般
分子病理

- 病理学講座
主任教授 - 宇於崎 宏
人体病理全般
消化器の病理

- 医療技術学部 臨床検査学科
教授 - 藤井 晶子
人体病理学全般
腎生検

- 病理学講座
准教授 - 菊地 良直
人体病理学全般
骨軟部腫瘍
癌微小環境

- 病理学講座
助教 - 安井 万里子
人体病理全般

- 病理学講座
助教 - 土谷 麻衣子
人体病理学
口腔病理学

- シニアレジデント
- 氷見 敦
人体病理全般(研修中)
上記の他、非常勤病理医7名(骨軟部、消化管、口腔、腎、リンパ腫・血液)により専門的な病理診断が行われています。
