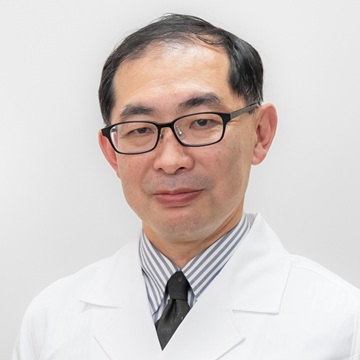脳神経内科・神経筋電気診断センター
診療内容・特色
脳神経内科では、神経系(脳、脊髄、末梢神経、筋)の器質的な(精神的なものではない)疾患を対象に診療を行っております。症状としては頭痛、しびれ、めまい、ものが二つに見える、呂律が回らない、手足が動かない、ふるえる、歩行の障害など多岐にわたります。当科では地域の医療機関と連携しながら、脳卒中、脳炎、髄膜炎などの急性期疾患や、パーキンソン病、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症などの神経難病から片頭痛など一般的な疾患まで対象として診療しております。
- 受診を考えられる方へ
- 上記のような症状が気になる方は、どうぞ受診をご検討下さい。ただし、かかりつけ医等にご相談の上、紹介状(診療情報提供書)をご持参ください。
- 他医療機関の方へ
- 神経疾患が疑われる患者さんのご紹介をお受けいたします。画像データがある場合はCD-ROMにて診療情報とともに患者さんにお渡しください。特定機能病院としての高度外来・入院機能を維持するために、診療方針の決まった患者さんについては積極的に地域に逆紹介しています。
当科の特色として、以下に挙げるような高度な医療体制が整備されており、重点を置いている疾患領域があります。
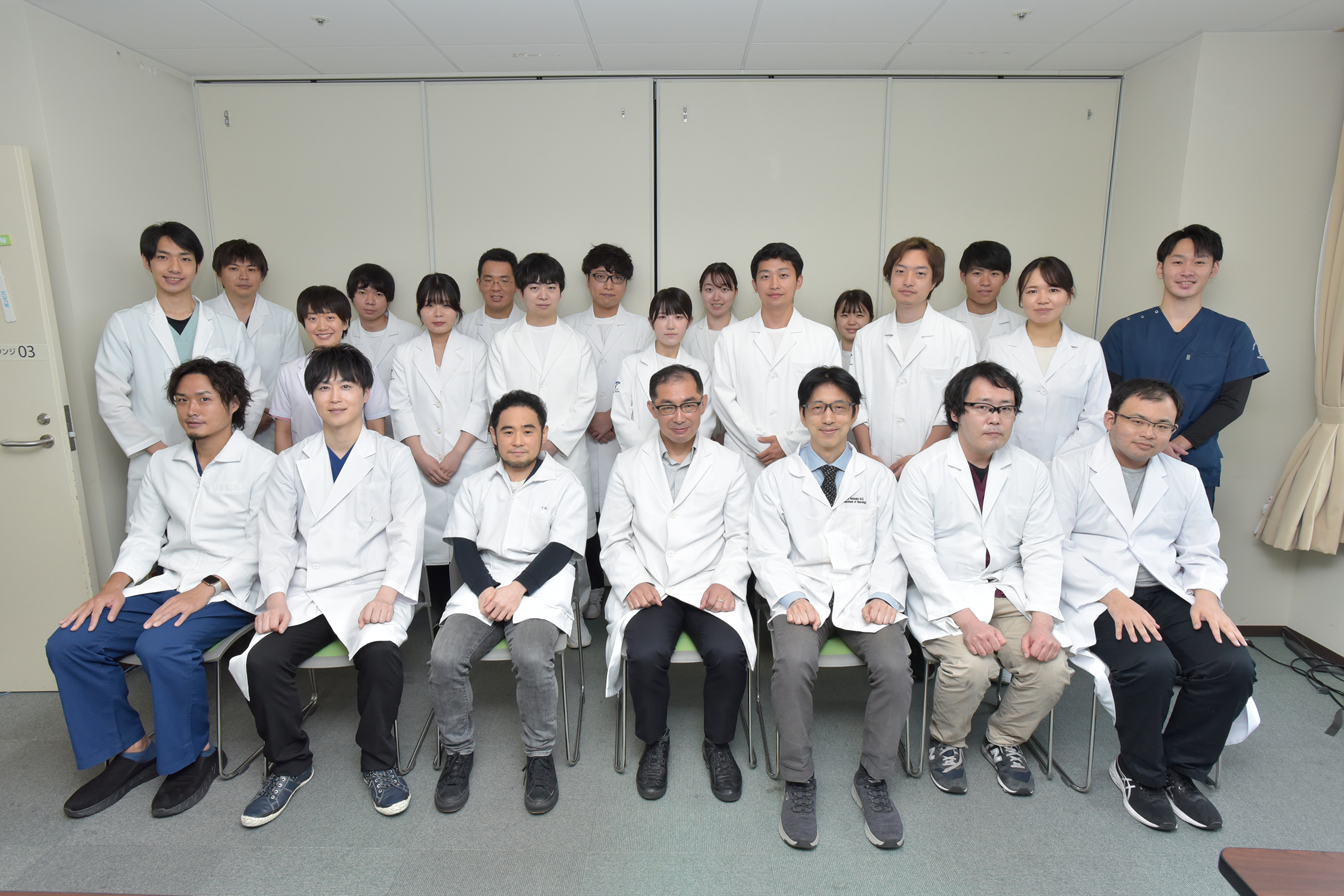

一次脳卒中センターコア施設
当院は脳卒中学会指定の一次脳卒中センターコア施設として24時間365日脳卒中患者を受け入れております。受診・搬送時は救急科、脳神経内科、脳神経外科の3科で対応します。超急性期に行う静脈的血栓溶解療法や機械的血栓回収療法に対応しています。その後はリハビリテーション科と連携し、急性期後はご自宅への退院やリハビリテーション病院への転院を目指します。
神経筋電気診断センター
針筋電図、神経伝導検査、体性感覚誘発電位(SEP)、超音波などの生理学的検査法を駆使して、脊髄・末梢神経・筋疾患を診断する分野を、神経筋電気診断学といいます。
当科は以前より園生雅弘前教授がこの分野の専門家として全国からの紹介を受けており、2014年から「神経筋電気診断センター」として公示しまして、医療機関からのご相談をお受けしております。
中央検査部とも協力し、日本臨床神経生理学会専門医・専門技術師総計14名を中心に診療にあたっています。園生雅弘教授も当センターにもちろん継続して勤務されております。
引き続き他医療機関からの紹介患者さまを、脳神経内科外来を通して受け付けております。
当センターへのご紹介については、脳神経内科外来にお問い合わせ下さい。
脊髄脊椎病センター
脳神経内科、整形外科、脳神経外科が連携して脊髄脊椎疾患の診断治療を行っています。当科併設の神経筋電気診断センターと連携して、適格な診断から最善の治療につなげる体制で診療にあたります。頚椎症、視神経脊髄炎、多発性硬化症、脊髄硬膜動静脈瘻、脊髄腫瘍、筋萎縮性側索硬化症などの診断において最善の診療を目指します。
パーキンソン病・パーキンソン関連疾患
パーキンソン病およびパーキンソン関連疾患の診断と治療に力を入れています。これらの疾患を専門とする医師による診察の上、神経心理学的評価、CT・MRI・SPECTなどの画像検査により診断します。パーキンソン病については多彩な症状の把握と処方の最適化をめざす丁寧な診療を心がけています。 一部の患者さんには臨床研究へのご協力をお願いしています。
神経免疫疾患
免疫系の異常により神経筋に障害を来たす疾患が多数あります。重症筋無力症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎 (CIDP)、 多巣性運動性ニューロパチー(MMN)、ランバート・イートン筋無力症候群などは画像診断や血液検査だけでは診断がつかないことも多く、電気生理学的検査が重要な疾患です。当科で最も診断に注力している部門で、研究や治験も積極的に行っております。 多発性硬化症、視神経脊髄炎、抗MOG関連疾患など中枢神経系の免疫疾患についても最新のエビデンスにもとづいた最善の診療を目指します。
希少難病
脳神経内科の領域には多くの希少難病がありますが、その一部では近年画期的な治療法が生まれています。アミロイドーシスはアミロイドと言われる異常なたんぱく質がさまざまな臓器に沈着し障害を引き起こすという疾患ですが、そのうちトランスサイレチン型アミロイドーシスに対しては異常蛋白を安定化させアミロイドに変化するのを抑制するビンダケル®やオンパットロ®による治療を行います。脊髄性筋萎縮症(SMA)は筋肉を動かすために脊髄にある運動神経細胞が変化するために徐々に手足の力がはいらなくなる疾患ですが、その原因の多くがSMN1遺伝子の異常によりSMNという特殊なたんぱく質が欠乏するためであることがわかっています。スピンラザ®、エブリスディ®などの新しい治療により、このSMN蛋白の遺伝子治療を行うことができます。
物忘れ外来
当科では物忘れ専門外来を完全予約制で受けております。物忘れや認知症を心配されている方、高次脳機能障害の評価をご希望の方を対象とした外来です。診断・評価を行い、その後の継続的な診療はかかりつけ医療機関で受けて頂きます。かかりつけ医がいる場合は診療情報提供書を持参の上、必ず身近なご家族・介護者が同伴して受診してください。当科での診断・評価後はかかりつけ医の元に通院していただくことになります。
頭痛診療
頭痛の診断は実は専門性が高い領域です。特に片頭痛の治療成績は近年の治療の進歩により大きく改善しています。現時点では専門外来を設けておりませんが、頭痛診療に力を入れています。特に重症の片頭痛の方は一度ご相談ください。
スタッフ

- 講師
- 神林 隆道
臨床神経学
神経筋電気診断学
(臨床神経生理学)
脳卒中
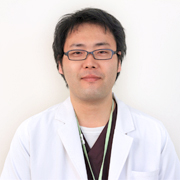
- 助教
- 千葉 隆司
臨床神経学
神経筋電気診断学
(臨床神経生理学)

- 臨床助手
- 松倉 清司
臨床神経学

- 臨床助手
- 向井 泰司
臨床神経学

- 臨床助手
- 萩原 夕紀
臨床神経学

- 臨床助手
- 藤井 勇基
臨床神経学

- 臨床助手
- 鈴木 郁
臨床神経学

- 臨床助手
- 難波 広人
臨床神経学

- 臨床助手
- 近藤 あむろ
臨床神経学

- 客員講師
- 永井 知代子
臨床神経学
神経心理学
高次機能障害

- 生理学講座
講師 - 磯尾 紀子
臨床神経学
認知症

- 医療技術学部
非常勤講師
- 塚本 浩
臨床神経学
神経筋電気診断学
(臨床神経生理学)
脳卒中

- シニアレジデント
- 黒澤 豪
臨床神経学

- シニアレジデント
- 和田 彩令奈
臨床神経学

- シニアレジデント
- 井上 雅人
臨床神経学

- シニアレジデント
- 中村 仁
臨床神経学

- シニアレジデント
- 山田 紗耶
臨床神経学

- 医師
- 新井 謙
臨床神経学

- 医師
- 村嶋 英治
臨床神経学

- 医師
- 高橋 和沙
臨床神経学

- 医師
- 大石 知瑞子
臨床神経学
神経筋電気診断学
(臨床神経生理学)

- 医師
- 溝井 令一
臨床神経学
神経筋電気診断学
(臨床神経生理学)

- 医師
- 此枝 史恵
臨床神経学
神経筋電気診断学
(診療神経生理学)

- 医師
- 上田 優樹
臨床神経学

- 医師
- 川上 真吾
臨床神経学
神経筋電気診断学
(臨床神経生理学)

- 医師
- 猪狩 龍佑
臨床神経学

- 医師
- 宮地 洋輔
臨床神経学
神経筋電気診断学
(臨床神経生理学)
脳卒中、頭痛

- 医師
- 山﨑 純
臨床神経学

- 医師
- 古川 裕一
臨床神経学

- 非常勤講師
- 尾方 克久
臨床神経学
筋肉病学

- 非常勤講師
- 仙石 錬平
臨床神経学
神経病理学
専門外来
認知症に対する物忘れ外来と頭痛外来を、通常の外来と同じ時間帯で診療しています。
物忘れ外来
超高齢化社会の到来とともに認知症は急速な勢いで増加しています。認知症の中には適切に治療すれば治る病気も含まれており、またアルツハイマー病では進行を遅らせるための薬物療法が可能です。当外来では予約でお待たせすることなく受診していただいたその日にすぐ診療を開始し、認知症の早期発見、早期治療介入を目指します。
頭痛外来
片頭痛や緊張型頭痛、群発頭痛といった機能性頭痛を始め、あらゆる頭痛を対象に診療します。
外来受付
- 03-3964-1211(代)
- 内線30208
- フロアマップ
- 再診予約・変更電話
-
TEL03-3964-8528
受付時間(月~金)13:00~17:00 - 医療連携室(予約専用)
- 初診で紹介状をお持ちの方は、医療連携室にて予約をお取り致します。
TEL03-3964-1498
電話予約時間(平日)8:30~17:00 (土曜日)8:30~12:30