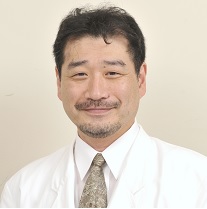小児科
診療内容・特色
こどもが病気になったら、まず受診するのが小児科です。当科では、日常よく遭遇する小児疾患に対する診療を重視しており、月〜土曜の週6日午前中に一般外来を設けて、小児科専門医を中心に診療を行っています。必要に応じて外来での検査、点滴などの治療を行い、また状態によっては入院し治療・検査を行います。けいれん・意識障害などの重症患者の受け入れ体制も整備し、二次救急、三次救急の対応にも力を入れています。
当科で扱う専門領域としては、神経・アレルギー・内分泌・代謝・栄養・循環器・免疫・血液・悪性腫瘍・腎・発達などがあり、それぞれ専門外来を開いています。また、当院は東京都に指定された総合周産期母子医療センターを有し、生まれたばかりの低出生体重児などの診療にあたるNICU(新生児集中治療室)にて、地域の産婦人科医のご紹介を通して入院を受け付けています。
急性疾患の救急対応から慢性疾患の長期管理に至る医療と、小児の健全な育ちを守る小児保健の重要性を常に意識し、地域に密着した成育医療の充実に貢献したいと考えております。
スタッフ

- 助教
- 森田 清子
新生児学

- 助教
- 米田 康太
新生児学

- 助手
- 小寺 美咲
新生児学

- 助手
- 岡 俊太郎
新生児学

- 助手
- 蔵本 怜
小児循環器学

- 助手
- 眞下 秀明
小児神経学

- 助手
- 嶋田 怜士
小児心身症
思春期(精神)医学

- 助手
- 髙宮 聖実
小児内分泌・代謝学

- 助手
- 治山 芽生
小児消化器病学
小児肝臓病学

- 助手
- 友利 伸也
小児腎臓病学

- 助手
- 計田 真彦
小児アレルギー・免疫学

- 助手
- 池田 啓一郎
小児アレルギー・免疫学

- 臨床助手
- 置塩 英美
新生児学

- 臨床助手
- 山本 美佳智
小児感染症学

- シニアレジデント
- 武村 真

- シニアレジデント
- 木村 将士

- シニアレジデント
- 平野 桜子

- シニアレジデント
- 伊藤 祐三

- シニアレジデント
- 飯山 徳子

- シニアレジデント
- 関野 裕太

- シニアレジデント
- 友部 まり

- シニアレジデント
- 岡澤 賢

- シニアレジデント
- 青柳 早織

- シニアレジデント
- 片平 美耶

- シニアレジデント
- 風祭 麗奈

- シニアレジデント
- 田近 良孔

- 医師
- 山本 和奈

- 医師
- 堀江 恭子

- 非常勤講師
- 黒田 友紀子
臨床遺伝学

- 非常勤講師
- 磯島 豪
小児内分泌・代謝学

- 非常勤講師
- 浦田 晋
小児循環器学

- 非常勤講師
- 大和田 啓峰
小児精神学
小児画像診断

- 非常勤助手
- 中井 まりえ
小児神経学

- 非常勤医師
- 望月 大史
小児内分泌・代謝学

- 非常勤医師
- 疋田 敏之
小児神経学

- 非常勤医師
- 小山 隆之
小児アレルギー・免疫学

- 非常勤医師
- 三重野 孝太郎
小児アレルギー・免疫学
専門外来
神経外来
小児の神経外来の対象は、てんかん、脳性麻痺、発達障害、代謝疾患、脳血管障害、末梢神経障害、筋疾患など、極めて多岐にわたりますが、全ての領域に対応します。
熱性けいれん重積や急性脳症、髄膜炎などの急性疾患に対しても、豊富な経験を有する小児神経専門医が診療にあたっています。
神経疾患入院数:年間約130例(対象期間:2023年度)
長時間ビデオ脳波検査:年間約20例
免疫・アレルギー外来
新たに開設した小児アレルギーセンターにて、ますます増えていく食物アレルギー、アトピー、喘息などの小児アレルギー疾患に対して、適切な検査とアドバイスをしていくことで、薬剤の効果を高めるような指導を心がけています。
また、診断の困難な小児の免疫疾患に対して、専門家が適切な検査・治療計画をたてて対応します。
食物負荷試験:年間300例
発達外来
NICUで経過をみていた小児を中心に、その神経学的発達を注意深く見守り、適切なアドバイスを心がけています。
NICU入院数:年間約300例(対象期間:2023年度)
内分泌・代謝外来
低身長症、甲状腺機能異常症、糖尿病、思春期早発症など小児期の診断・治療が特に大切な内分泌疾患に力を注いでいます。低身長をはじめとする負荷試験が必要な場合は外来または入院で検査を行います。
内分泌疾患入院数:年間約30例(対象期間:2023年度)
循環器外来
新生児・乳児から学童まで、心雑音やチアノーゼ、不整脈などの疾患を中心に、小児に負担をかけない胸部X線写真・心電図・超音波検査などを用いて診断・治療を行います。
より高度の検査を必要とする場合は、入院のうえ検査を行います。
循環器疾患入院数:年間約30例(対象期間:2023年度)
腎臓外来
3歳児健診や学校検尿で発見された血尿・蛋白尿のフォローから腎炎・ネフローゼ症候群の治療まで、専門医がこどもの立場にたった診療を行っています。また、水腎症をはじめとした腎尿路疾患や夜尿症・頻尿についても、精力的に診療しています。
腎・尿路疾患入院数:年間約30例(対象期間:2023年度)
血液・腫瘍外来
血液疾患と腫瘍性疾患を主に診察しています。特に小児がんは他診療科とも協力して、患者さんに適切な診断と治療を提供しています。当院は日本小児がん研究グループ(JCCG)に属し、小児がんの臨床研究に参加していますので、全国と同じ水準の医療を受けることができます。
血液腫瘍疾患入院数:年間約10例(対象期間:2023年度)
糖尿病外来
乳幼児健診外来
総合周産期母子医療センターで経過を診ていた新生児・乳児を中心に、経過をみつつアドバイスをしています。
感染(予防接種)外来
遺伝相談外来
生まれつきの原因による疾患(先天性疾患)は心疾患、難聴、口唇口蓋裂などの身体合併症や発達の遅れなども含まれ、一人のお子さんがこれらを複数持ち合わせることもあります。この場合は先天異常症候群と呼ばれる特定の基礎疾患の存在に留意が必要です。遺伝外来では、これらのお子さんの原因診断を検討するとともに、診断に伴う原因理解、健康管理や次子・家族への影響、社会資源などを含めた情報提供やコーディネートに関わります。
思春期(児童心理)外来
外科疾患につきましては、小児外科等と密接に連携をとって対応しております。その他にも心理外来などの外来枠がございますのでご相談ください。
外来受付
- 03-3964-1211(代)
- 内線30229
- フロアマップ
- 再診予約・変更電話
-
TEL03-3964-8512
受付時間(月~金)13:00~17:00 - 医療連携室(予約専用)
- 初診で紹介状をお持ちの方は、医療連携室にて予約をお取り致します。
TEL03-3964-1498
電話予約時間(平日)8:30~17:00 (土曜日)8:30~12:30